Medical
診療案内
舌下免疫療法について
スギ花粉症・ダニアレルギーに対する舌下免疫療法(SLIT)について
スギ花粉症の舌下免疫療法薬剤の出荷調整中のため、新たに舌下免疫療法を開始希望の方は、ご来院の際にご確認ください。
舌下免疫療法はアレルゲン免疫療法とも呼ばれ、病因アレルゲンを投与していくことにより、アレルギーに暴露された場合に引き起こされる症状を緩和すること が期待できます。現在、スギとダニに対する舌下免疫療法用のアレルゲンエキスが発売されています。今まで、一般的に使われているアレルギーの薬や手術は対症療法と呼ばれ、症状を一時的に緩和させることが目的でしたが、アレルゲン免疫療法では2割ほどの人に対して根治的な効果があると報告されています。
しかし、舌下免疫療法にもデメリットがあります。3~5年の治療期間がかかり、即効性を期待できません。スギ花粉症の方は、スギ花粉飛散期から投与開始はできません。すべての人に効果が期待できるわけではなく、副反応の問題もあります。 この治療法は、正しく使用法を守り、薬に対する理解がなければ開始することができません。このため、この薬はすべての医療機関で処方できるわけではなく、講習会を受講し、登録された施設でしか処方できません。 ご希望の方は、受診した際にご相談ください。
効果
くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみなどの季節性(スギ花粉症)・通年性(ダニアレルギー)アレルギー性鼻炎の症状に効果があるとされていますが、すべての患者さんに効果を示すわけではありません。 2割くらいの人は症状がほとんど消失し、6割くらいの人は症状が緩和し従来からあるアレルギーの薬を使う量が減少します。しかし残念ながら2割ほどの人には全く効果が期待できません。 効果があるかないかについては、投与前に判断ができず、薬を使ってみて初めてわかります。対象者
治療対象は「スギ花粉症患者」「ダニアレルギーによる通年性アレルギー性鼻炎患者」であり、アレルギー検査による確定診断が必要です。 舌下免疫療法は、スギおよびダニの治療薬も、12歳以下でも服薬可能となっています。舌下免疫療法が受けられない方
この治療法は今まで治療した病気や、現在内服している薬によって投薬できない場合もあります。 重症の気管支喘息で治療中の方は、舌下免疫療法により喘息発作を誘発する恐れがあるため投与できません。 悪性腫瘍、または免疫系に影響を及ぼす重篤な全身性の疾患(たとえば、自己免疫疾患や免疫複合体疾患、または免疫不全症など)を治療中の方には、薬の有効性や安全性に影響を与える可能性があり投与できません。 重症な心疾患・肺疾患・高血圧症がある方は、強い副反応が出た時の影響が大きいため主治医の先生とご相談ください。 また、非選択的β遮断薬(降圧剤)、全身性ステロイド薬などを服用している場合は舌下免疫療法を行えないことがあります。現在飲んでいる薬は必ず受診時にお申し付けください。副反応について
一般的に服薬開始から1ヶ月くらい、服用してから30分以内、スギ花粉症の方はスギ花粉飛散期に副反応がおこりやすいとされています。治療開始から1ヶ月は増量期といって、薬の量がだんだん多くなっていきます。 この時期に副反応が起こることが多いため、とくに初回投与時は医師の監督のもと投与が行われ、少なくとも30分 は院内に留まっていただく必要があります。よく見る副反応として、口内炎、舌の下の腫れ、のどのかゆみ、耳のかゆみ、頭痛などがあります。 また、アナフィラキシーといった全身性の強い副反応が起こる可能性もあり、副反応に対する適切な対処法と理解が求められます。注意すべきこと
指定された量をきちんと飲み、自己判断で服用を中止しないでください。 この治療には即効性はなく、治療期間として3~5年継続することが重要で、スギ花粉が飛散していないときも含めて365日毎日続けて服用してください。 効果があって終了した場合でも、その効果が弱くなる可能性があります。 服用前後2時間くらいは、副反応を起こしやすくするため激しい運動、アルコール摂取、入浴などを避けてください。薬の効果を保つために服用後5分はうがい、飲食をしないでください。 病状管理のため落ち着いても、月に1回は来院してください。 スギ花粉症の方は、スギ花粉飛散期はスギに対する過敏性が高まっているため副反応が強く出る可能性があります。このため治療開始時期については、6月から12月までが妥当であると考えられています。
嚥下内視鏡検査(VE)

食事のときに「むせる」「飲み込みにくい」と感じることはありませんか?
飲み込む力(嚥下機能)が低下すると、食べ物や飲み物が誤って気管に入る(誤嚥)ことが増え、誤嚥性肺炎のリスクが高くなります。
嚥下内視鏡検査(VE検査)は、鼻から細いカメラ(内視鏡)を入れて、のどの動きや食べ物の流れを観察する検査です。X線を使わないため、放射線を浴びる心配がなく、ご高齢の方や体力が低下している方でも安心して受けられます。飲み込みに不安がある方の状態を詳しく調べ、安全に食事を続けるための対策を考えるのに役立ちます。この検査の結果をふまえて、今後の食事形態や食事時の姿勢の調節、嚥下訓練の適応、方針を決定します。
嚥下内視鏡検査のメリットと注意点
メリット
- 実際に食べているものを使って検査できる
- のどの動きや食べ物の流れを詳しく観察できる
- X線を使わないので、何度でも検査できる
- 造影剤を使わないため、アレルギーの心配がない
- 機器が小型なので、病院以外(自宅や施設など)でも検査できる
注意点
- 飲み込む瞬間(食道に入る動き)は見えない
- 内視鏡を入れるときに少し違和感がある
- 気管の奥(気管の後ろ側)は直接見ることができない
- 検査中に誤嚥が起こることがある

地域でのサポート体制について
豊島区では、医師・歯科医師・歯科衛生士・管理栄養士・介護支援専門員(ケアマネージャー)などが協力し、在宅医療を支える取り組みを行っています。また、「口腔・嚥下障害部会」を設置し、専門的な支援を進めています。在宅での検査を希望される方は、まず主治医にご相談ください。
飲み込みに不安がある方は、お気軽にご相談ください。
嚥下内視鏡検査(VE検査)の流れ
検査の内容
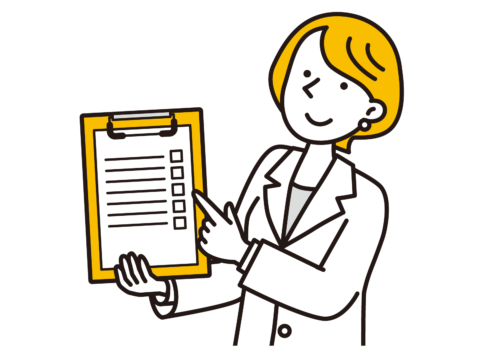
鼻の穴(鼻腔)から細いカメラ(内視鏡)を入れ、のど(咽頭)の様子を観察します。 そのまま内視鏡を入れた状態で、見やすいように食紅などで色をつけたとろみのない水、とろみのある水、ゼリー、または実際の食事を飲み込んでいただきます。
検査時間: 約15分です。
検査によるリスクについて
誤嚥や肺炎、窒息のリスク
検査では、飲み込む力を確認するために、少量の食べ物を口にしていただきます。 その際、誤嚥(食べ物が誤って気管に入ること)が起こる可能性があります。 ごくまれに、以下のリスクがあります。
誤嚥の量が多い場合、発熱や誤嚥性肺炎を引き起こすことがある。
誤嚥性肺炎が重症化することがあり、非常にまれですが、検査中に窒息する可能性があります。 検査中は、誤嚥が起こった場合にすぐ対応できるように、吸引機を準備しています。
その他のリスク
頻度は低いですが、以下の症状が出ることがあります。
鼻出血(鼻の中にカメラを入れるため)
のどの軽い出血 – 声帯やのどのけいれん
一時的なめまい(血圧の変化による失神)
この検査は、飲み込みの状態を詳しく調べ、安全に食事を続けるための大切なステップです。 ご不安なことがあれば、お気軽にご相談ください。

