Hearing Aid
補聴器
聞こえが悪いと感じたらすべきこと
-
耳鼻咽喉科を受診する
まずは耳鼻咽喉科で検査を受け、原因を調べてもらいましょう。難聴にはさまざまな原因があり、治療可能なケースもあります。- 耳垢(耳あか)による聞こえの低下
耳垢が詰まることで聞こえにくくなることがあります。耳鼻科で安全に除去できます。 - 中耳炎など炎症による耳の病気
急性中耳炎や滲出性中耳炎などが原因で、聞こえが悪くなることがあります。適切な治療で改善することが多いです。 - 耳の神経の病気
突発性難聴とはある日突然、片耳(または両耳)が聞こえにくくなる病気です。その他の疾患(メニエール病・騒音性難聴など)内耳や神経の問題が原因のこともあり、専門的な検査が必要です。発症から時間が経つと治療の効果が下がるため、できるだけ早く受診が必要です。 - 加齢による難聴(加齢性難聴)
高齢になると、徐々に聞こえが悪くなることがあります。補聴器の使用を検討することで、生活の質を維持できます。
- 耳垢(耳あか)による聞こえの低下
-
聴力検査を受ける
耳鼻科では、聴力検査を行いどの程度の難聴なのかを調べます。検査結果によって、適切な治療や補聴器の必要性が判断されます。 -
補聴器を検討する(必要な場合)
加齢性難聴や改善が難しい難聴の場合、補聴器の使用を考えることも重要です。補聴器を適切に使うことで、コミュニケーションが楽になり、認知症の予防にもつながります。- 補聴器の選び方
聴力や生活スタイルに合った補聴器を選ぶことが大切です。補聴器専門店や耳鼻科で相談すると良いでしょう。 - 補聴器の試聴・慣れる期間
すぐに聞こえが良くなるわけではないので、慣れるための期間が必要です。
- 補聴器の選び方
まとめ
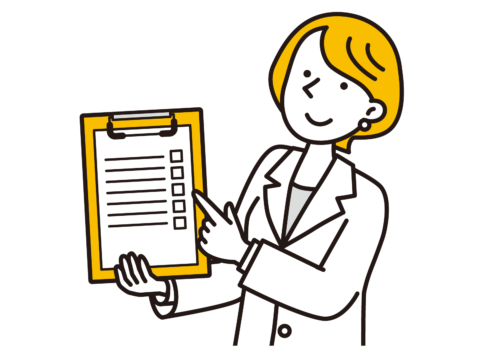
- 聞こえにくいと感じたら、まずは耳鼻科を受診!
- 耳垢や中耳炎など、治療で改善することもある
- 突発性難聴は早めの治療が大事!
- 加齢性難聴の場合は補聴器の検討も必要
放置せず、早めに専門医に相談することが大切です。
難聴と認知症について
難聴と認知症には深い関係があることが多くの研究で示されています。難聴が進行すると、認知症のリスクが高まる可能性があるため、早めの対応が重要です。
難聴と認知症の関係
-
認知負荷の増加
難聴になると、聞こえにくい音を理解しようと脳が余分にエネルギーを使います。その結果、記憶や判断など他の認知機能に使う余力が減り、認知機能の低下につながる可能性があります。 -
社会的孤立
難聴の人は会話が難しくなり、コミュニケーションを避けるようになることがあります。これが孤独感やうつを引き起こし、認知症のリスクを高める要因となります。 -
脳の萎縮
聞こえない状態が続くと、脳の聴覚に関わる部分の活動が低下し、脳の萎縮が進む可能性があります。特に側頭葉や海馬(記憶を司る部分)に影響を与えることが示唆されています。
難聴による認知症リスク
2020年、世界的に権威のある医学誌ランセットが「認知症の40%は予防可能な12の要因により起こると考えられ、そのなかで最大の危険因子は難聴」と発表しました。
難聴8%、教育7%、喫煙5%、うつ4%、社会的孤立4%、外傷性脳損傷3%、高血圧2%、運動不足2%、大気汚染2%、過剰アルコール摂取1%、肥満1%、糖尿病1%
米ジョンズ・ホプキンス大学の研究では、
- 軽度の難聴 → 認知症のリスクが約2倍
- 中等度の難聴 → 約3倍
- 重度の難聴 → 約5倍
に上昇する可能性があると報告されています。
対策と予防
-
早期発見・早期対応
- 定期的に聴力検査を受ける(特に高齢者や難聴リスクの高い人)
- 聞こえにくいと感じたら放置せず、耳鼻科を受診する
-
補聴器や人工内耳の活用
補聴器の適切な使用が認知機能の低下を防ぐ可能性があるとされています。難聴を補うことで、脳の活動を維持し、社会的交流も保ちやすくなります。 -
コミュニケーションを続ける
- 家族や友人との会話を大切にする
- 読書や音楽を楽しむ
- グループ活動に参加する(地域のサークルなど)
-
健康的な生活習慣
- 運動(ウォーキングや体操)
- バランスの良い食事(地中海食など)
- 十分な睡眠
補聴器について
1. 補聴器とは?
補聴器の基本的な役割
補聴器は、聴力が低下した人がより良く音を聞き取れるようにするための医療機器です。主な役割は以下のとおりです。
- 小さな音を増幅し、聞き取りやすくする
- 会話の明瞭度を向上させ、コミュニケーションをサポートする
- 周囲の環境音を調整し、快適な聞こえを提供する
補聴器の仕組み
補聴器は、主にマイク・アンプ(増幅器)・スピーカー(レシーバー)・電源の4つの基本部品で構成されています。
-
マイク(マイクロフォン)
- 周囲の音を拾い、電気信号に変換する
-
アンプ(増幅器)
- 音の大きさを調整し、適切に増幅する
- ノイズを抑え、聞き取りやすく処理する
-
スピーカー(レシーバー)
- 増幅された音を耳の中へ届ける
-
電源(バッテリー)
- 補聴器の動作を支える(使い捨て電池や充電式がある)
デジタル補聴器の特徴
現在主流のデジタル補聴器は、コンピューターチップを搭載し、以下のような機能を備えています。
- 騒音を抑える(雑音抑制機能)
- 言葉をより明瞭にする(音声強調機能)
- 環境に応じて音を調整する(自動調整機能)
- ハウリング(ピーピー音)を抑える(ハウリング抑制機能)
補聴器は、使用者の聴力や生活環境に合わせた調整が重要です。適切な機器を選び、調整を行うことで、より快適な聞こえを得ることができます。
2. 補聴器の種類と特徴

補聴器にはいくつかの種類があり、形状や機能が異なるため、使用者の聴力やライフスタイルに合わせた選択が重要です。以下に、主な補聴器の種類と特徴を紹介します。
① 耳かけ型(BTE: Behind-The-Ear)
特徴
- 耳の後ろに掛けるタイプで、本体からチューブを通して音を耳に届ける
- 軽度~高度難聴の方まで幅広く対応
- 最近は小型化が進み、目立ちにくいデザインも増えている
メリット
- 聴力レベルに合わせた幅広い調整が可能
- 電池寿命が長く、充電式モデルも選べる
- 湿気や汚れに強く、耐久性が高い
デメリット
- メガネやマスクと干渉することがある
- 耳の後ろに機器があるため、装着感に違和感を感じることも
おすすめの人
- 幅広い難聴レベルの方
- メンテナンスのしやすさを重視する方
- 耳の形状に個別の適合が難しい方
② 耳あな型(ITE: In-The-Ear)
特徴
- 耳の穴に収まるタイプで、オーダーメイドが基本
- 軽度~中等度難聴の方に適している
- 「フルサイズ」「カナル(小型)」「完全耳あな型(CIC)」など、サイズに応じた種類がある
メリット
- 目立ちにくく、自然な装着感
- 眼鏡やマスクと干渉しにくい
- 電話やヘッドホンを使いやすい
デメリット
- 小型のものほど電池寿命が短い
- 耳の形状によってはフィットしにくい
- 湿気や耳垢の影響を受けやすい
おすすめの人
- 目立ちにくい補聴器を希望する方
- メガネやマスクを頻繁に使用する方
- 会話中心の生活スタイルの方
③ ポケット型(Body Aids)
特徴
- 本体をポケットや首から下げて使用し、イヤホンで音を届けるタイプ
- 高度~重度難聴に対応可能
メリット
- 大きな音を出せるため、重度難聴にも対応
- 操作がしやすく、高齢者にも使いやすい
- 電池寿命が長い
デメリット
- 本体をポケットや首からぶら下げる必要があり、持ち運びがやや不便
- コードが邪魔になりやすい
- 見た目が目立つ
おすすめの人
- 高度~重度難聴の方
- 操作のしやすさを重視する方
- 補聴器の装着が難しい方(手の不自由な方など)
④ 骨伝導補聴器
特徴
- 骨を振動させて内耳に直接音を届けるタイプ
- 伝音難聴(外耳や中耳に問題がある場合)に適している
メリット
- 外耳や中耳に問題がある方でも音を伝えやすい
- 耳をふさがずに装着できる
デメリット
- 通常の補聴器に比べて音質が劣る
- 装着の違和感を感じる場合がある
おすすめの人
- 外耳・中耳の病気や手術後で通常の補聴器が使えない方
- 眼鏡型補聴器を希望する方
⑤ メガネ型補聴器
特徴
- メガネのツル部分に補聴器を内蔵したタイプ
- 骨伝導タイプと気導タイプがある
メリット
- メガネと一体化しているため、装着しやすい
- 骨伝導モデルなら外耳が使えない人にも有効
デメリット
- メガネと一緒に使う必要があり、選択肢が限られる
- 補聴器の調整や修理が必要な場合、メガネも使えなくなる
おすすめの人
- 普段からメガネをかける人
- 骨伝導補聴器が必要な人
まとめ:補聴器の選び方
補聴器を選ぶ際は、以下のポイントを考慮すると良いでしょう。
- 聴力レベル(軽度・中等度・高度・重度難聴)
- 使用環境(家庭・仕事・外出時など)
- 装着のしやすさ(メガネやマスクの併用、操作のしやすさ)
- 目立ちにくさ(デザインやサイズ)
耳鼻科や補聴器専門店で相談しながら、自分に合った補聴器を選ぶことが重要です。
3. 補聴器が必要なサイン
聴力低下のチェックリスト
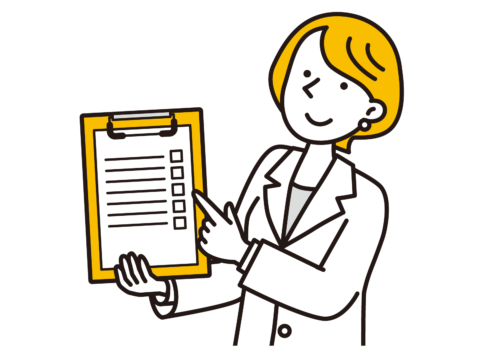
聴力は徐々に低下するため、自分では気づきにくいことがあります。以下のチェックリストで、聞こえの状態を確認してみましょう。
日常生活でのチェック
- 家族や友人との会話で、聞き返しが増えた
- 会話の途中で「え?」「もう一度言って」と言うことが多い
- 周囲の人から「声が大きい」と言われる
- 相手が小さい声や早口で話すと、理解しにくい
- テレビやラジオの音量を以前より大きくしないと聞こえない
- 電話の声が聞き取りにくいことがある
環境音の聞こえ方チェック
- 玄関のチャイムや電話の呼び出し音に気づきにくい
- 車のクラクションや後ろから来る自転車のベルが聞こえにくい
- 電子レンジやアラームの音を聞き逃すことがある
- 雨の音や風の音に気づかないことがある
会話の聞き取りチェック
- 複数人での会話についていけないと感じる
- 騒がしい場所(レストラン・駅など)での会話が聞き取りにくい
- 聞こえても、何を言っているのかはっきり分からないことがある
- 特定の人(女性・子ども・小さい声の人)の声が聞き取りにくい
聴こえによるストレスチェック
- 聞き返すのが面倒で会話を避けることがある
- 人と話すのが億劫になり、外出が減った
- 聞こえないことで誤解が生じ、イライラすることがある
- 以前に比べて、会話が疲れると感じる
上記のチェックリストで気になることがありましたら、耳鼻科で聴力検査をお勧めします。
ご自宅でも簡易的にアプリを使った『聞こえのチェック』が体験できます。
「みんなの聴脳力チェック」アプリを使ってヒアリングフレイルを予防しよう!
「みんなの聴脳力チェック」は言語聴取脳力をアプリで簡単にチェックできるツールです。|ユニバーサル・サウンドデザイン株式会社
4. 補聴器のよくある質問(Q&A)
「補聴器はどのくらいの期間で慣れますか?」
補聴器は単に「音を大きくする」道具ではなく、脳の聞く力を再訓練するためのものです。そのため、3か月以上かけて脳を慣らすことが重要になります。
脳が補聴器に慣れるプロセス
-
最初の数週間:
- 音が大きく感じる、違和感がある
- 雑音や自分の声が不自然に聞こえる
-
1~3か月:
- 脳が新しい聞こえ方に適応し始める
- 言葉の聞き取りが少しずつ改善する
-
3か月以降:
- 会話がより自然に聞こえるようになる
- 騒がしい場所でも聞き取りやすくなる
なぜ脳を慣らすのに時間がかかるのか?
難聴が進むと、脳の「言葉を聞き分ける力」も衰えます。補聴器をつけてもすぐには元のように聞こえず、脳が新しい音に慣れるためのトレーニングが必要になります。
スムーズに慣れるためのコツ
- 毎日少しずつ装着時間を増やす
- 静かな場所で家族や友人と会話をする
- テレビの音量を適切に調整しながら聞く
- 補聴器の調整をこまめに行う
補聴器は「継続がカギ」
途中で外してしまうと、脳がなかなか適応できず、効果が得られにくくなります。焦らず、少しずつ脳を慣らしていくことが大切です。
定期的な補聴器販売店での点検、音に対する反応を見ながら調整をする必要があります。
「保険適用はありますか?」
残念ながら、補聴器の購入は、健康保険や生命保険、介護保険などの適用にはなりません。
高度難聴の場合は身体障碍者手帳が交付されることがあります。これにより補聴器購入の助成を受けることができます。
中等度難聴の方でも、お住いの地区によって補助が出る場合があります。役所にご確認のほどお願いいたします。
また、補聴器購入において医療費控除を受けるためには、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会の認定する「補聴器相談医」による「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」が必要です。高齢者や年金受給中の人でも、確定申告をすれば補聴器の購入費用で医療費控除を受けることが可能です。当院でも発行が可能なため、ご相談ください。



